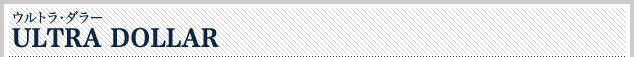嘘か事実か?絵空事ではないリアルなスパイ小説
田勢 康弘(日経経済新聞社コラムニスト)
「この人は将来、大変なミステリー作家になるのではないか」八年ほど前、私は『ジャーナリストの作法』という拙著で手嶋龍一氏についてこう書いたことがある。その理由として「日本人には珍しいくらい世界の諜報活動に詳しい人で、二度のワシントン勤務とボン支局長時代の欧州情報で、環境は整ったのではないかと思っている」と書いた。NHKを辞めた超大物記者が、私の “予言”通り、スパイ小説を書いた。
一ヶ月ほどかけて一ページ一ページ、じっくり読んだ。その結果、私はこの小説の書評役としてはきわめて不適任であることがわかった。何気なく書かれているディテールの一つ一つが膨大な情報量を伴って私に襲い掛かってくる。そのディテールの恐ろしさにまず震え上がってしまい、読者としての、あるいは書評家としての冷徹な目で読み続けることができなかったのだ。ディテールの恐ろしさは、それが絵空事ではないことを、私が知っているから感じるのだろう。
北朝鮮の偽百ドル紙幣がこの小説の主人公である。朝鮮半島のみならず、米国、中国、ロシア、ウクライナ、フランス、そして日本。この手の小説のストーリーを明かしてしまうほどやぼなことはないが、ちりばめられた数々の「事件」や「情報」のほとんどが現実のものであり、それらの断片を紡いでいくことによって、巨大なジグソーパズルが完成する。
完成したジグソーパズルを眺めてみて読者が気づくのは、この小説が各国諜報機関の情報戦を描くのがねらいではなく、パズルの背景にうっすらと、しかし確実に視野に入ってくる巨大な絵を描くためのものだということである。それは窮鼠猫をかむごとき北朝鮮の犯罪や、ロシアから欧米へと路線を大きく転換したウクライナのお追従外交などではなく、米国と、そして中国という大国の世界戦略という風景画なのである。
その中での貧しい、そして悲しい、外交などと呼ぶことさえためらわれる日本外交。著者はこう記す。
「歴史への畏れを抱いた外交官だけが、組織内の栄達や目先の政治情勢に足をとられることなく、筋の通った交渉をやり遂げる。その志が公電のかたちをとって歴史に刻まれていく。外交の軌跡を公電という形で記録に残さなくていいなら、恣意的な交渉に身を委ねればいい。その果てに国家や国民を裏切る決着を図ることすら可能だろう。だが、そうした行為は歴史への冒涜にほかならない」
一九九〇年の金丸信訪朝団から、今日の小泉純一郎首相の二度の訪朝にいたるまで、北朝鮮外交に関しては公電がきちんと残されていない。金日成・金丸会談で何が話されたか日本側には記録がまったくないし、小泉訪朝でもいまだに不明な部分が相当ある。おそらく著者がもっとも言いたかったのはこのことだろう。小説では外務省高官から最高機密が北朝鮮に流れている。それ以外の部分の大半が現実とぴたっと重なりあうだけに、この部分だけはフィクションであってほしいと思わずにいられない。
それにしても、この小説に登場するような華麗な人物たちとつきあったことがないので、彼らの身に着けているファッション、食事、ワイン、高級車、篠笛や浮世絵など私にはめくるめくばかりの世界だ。冒頭の浮世絵のオークションの場面で読者はまず腰を抜かしてしまうだろう。いずれの場面も、いつかどこかで同じ場面に作者自身が登場していたことがあるはずだ。出なければあそこまでリアルに描写できない。とすれば手嶋龍一という人物は、何者なのだろう。NHKという巨大組織は、この人物を等身大に捉えることに失敗した。凡庸な人間にあてはめるものさしでこの人物を量ろうとしたために、鉱脈の深さに気づくことはなかった。重要な場面で登場する妖艶な美女たち。映像で見る以上にイメージの世界の中で見事に像を結ぶ彼女たち。リアルな描写。説得力のある会話。この部分がフィクションなのかどうかは、私にもまったく見当がつかない。
月刊『現代』2006年4月号掲載