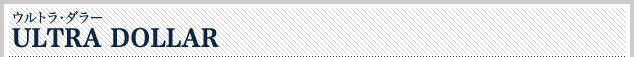十五年目の著者ノート 手嶋龍一
「テロの世紀」は突如として幕を開けた──。緊急報に接したのは、ホワイトハウスに程近いNHKワシントン支局に出勤する車のなかだった。ラジオの番組がブレーキング・ニュースに切り替わり、ニューヨークのワールド・トレード・センターに小型機らしきものが衝突したと伝えている。こうして私の「九・一一自爆テロ事件」は始まった。間髪を入れず、「大規模なテロ事件らしい」という通報が携帯電話に入ってきた。カメラクルーを現場に派遣する手配をしながら、国際テロ組織の仕業と断じた「大統領声明」を掴んでスタジオに駆け込もうとしたその時だった。ポトマック河を挟んで彼方に建つペンタゴンから黒々と煙が立ち上っているのが見えた。民間機をハイジャックしたテロリストたちは、アメリカ経済の中枢ばかりか、国防の司令塔にも襲いかかっている。まさしく同時多発のテロルだ。二〇〇一年九月十一日、澄み渡った初秋の朝の惨事だった。
超大国アメリカは、持てる力の限りを振り絞って反撃に出た。米本土の心臓部を衝いた国際テロ組織「アルカイダ」を抱え込んでいたアフガニスタンを標的に牙を剥いたのである。さらに一年半の後、サダム・フセイン率いるイラクを「悪の枢軸」の巨魁と断じて侵攻した。アメリカ軍の部隊は、イラク全土に散らばる疑惑の施設を隈なく探索し、核・生物・化学兵器の製造・貯蔵拠点を見つけだそうとした。だが、その匂いすら嗅ぎつけられなかった。「イラクに核・生物・化学兵器あり」というインテリジェンスは、フェイクだったのである。
われらが東アジアに巨大な力の空白が生じてはいないか──。アフガニスタンからイラクへと展開する「ブッシュの戦争」を憑かれたように追い続けていたわが胸中にそんな思いが宿り始めていた。アメリカが、九・一一事件に突き動かされて、軍事作戦の軸足を中東に大きく傾かせている間に、もうひとつの戦略正面たる東アジアでは抑止力が大きく殺がれている。その間隙を縫って、北朝鮮は核ミサイルの開発を密かに進め、中国は台湾海峡で制空・制海権を奪うべく周到な布石を打ちつつあった。
国産戦闘機の開発を巡って日米同盟に生まれた亀裂を描いた『ニッポンFSXを撃て』。湾岸戦争での日本外交の迷走ぶりを追った『一九九一年 日本の敗北』。私はそれまでにもこうしたノンフィクション作品を発表してきた。だが、東アジアに生じつつある巨大な「戦略的な空白」が現実の事象として地表に現れているのはごくわずかだった。多くが地底深くに伏流する事象は、ノンフィクションの対象になりにくい。やがて東アジアに生起する事態を物語の形で描いてみようと思い立ち、誕生したのが『ウルトラ・ダラー』だった。
「ブッシュの戦争」に一区切りがついたら、NHKから離れて執筆に専念しようと心に決めていた。日常の雑事から逃れて執筆に打ち込むため、チェサピーク湾に面した美しい港町セント・マイケルズに小さなコテージを借りた。昼夜の別なく大統領の動静を追い続ける日々からようやく解き放たれた。真っ青な湾を見下ろす高台から小さな通信機器を海に放り投げた爽快感は、いまでも鮮やかに憶えている。
毎日決まってランチに出かけるカフェでニューヨーク・タイムズを広げ、つい先頃まで共に取材をしていた仲間が書いた記事を気楽にながめる。そんな日々よ、永遠に続け、と願ったのだが、物語は三か月ほどで仕上がってしまった。
私のメッセージは果たして日本の読者に届くだろうか──。一抹の不安もあったが、幸い読者は物語をまっすぐに受け止めてくれた。だがなかには、手厳しい読み手もいた。「著者と語る」という催しでの出来事だった。会場が大阪だったこともあり、質問は率直で小気味よく、鋭いものばかりだった。
「本の帯には『これを小説だと言っているのは著者たったひとり』とありますが、どれが事実で、どこが物語なのか、ヒントをもらえませんか」
小説のスタイルをとっているのは、貴重な情報源を秘匿するのが狙いだったから、答えに窮してしまった。だが、大切な読者を無下にするわけにもいかない。
「困ったなあ。まあ、インテリジェンス・ワールドの出来事ですから、あなたがここは作り物と思う箇所は、意外にも──と申し上げておきましょう」
だが、手をあげた若い女性は、わが回答に少しも納得していない様子で、そのままやりすごせない雰囲気だった。
「ひとつだけ例をあげましょう。名のある評者が有力な雑誌の書評欄で、鎌倉山の学校で主人公がユーミンの歌詞を教材に日本語を学ぶ場面を取りあげ、いくら小説だからといってあまりに嘘っぽいと書いていました。じつは、このシーンは事実を忠実に写しとったもので、創作ではありません」
戦後のニッポンに彗星のように現れたインテリジェンス・オフィサー、佐藤優氏は、グレアム・グリーン著『ヒューマン・ファクター』を例に引きながら、諜報の世界を扱った物語の約束事に触れている(『ウルトラ・ダラー』新潮文庫版、解説より)。グリーン自身もかつてSIS・イギリス秘密情報部に勤務した履歴があり、そのため厳格な守秘義務を課せられていた。それゆえ、物語の執筆に当たっては、情報源を悟らせないよう「本当のような嘘」と「嘘のような本当」を巧みにブレンドしているのだと指摘している。
「手嶋龍一氏の場合も、ある巨大な国際的インテリジェンス・ネットワークから提供された文書資料の情報源を秘匿するためにインテリジェンス小説という手法をとったのだと評者は見ている」
私自身はいかなる意味でも諜報機関に身を置いた経歴がない。一方で、様々な国の情報機関を取材した経験はあるが、機微に触れる情報源を危険に曝したことはない。
ノンフィクションか、フィクションか──。そう問われれば、『ウルトラ・ダラー』にはノンフィクションとは言えない出来事が描かれている。その時点では未だ何ごとも起きてはいなかったのだから。アメリカ財務省の諜報チームに関する記述がその一例だろう。彼らは後にマカオの黒い銀行バンコ・デルタの摘発に乗り出すが、執筆時点では何も起きていない。このくだりを捉えて、「日々のニュースがこの物語を追いかけている」と評されたこともあった。
佐藤優氏は、過去に生起した事件を下敷きに架空の人物を設え、ふくらし粉を入れて膨らませた、いわゆる「ドキュメンタリー・ノベル」と、インテリジェンス小説は全く別の系譜に属すると言う。
「インテリジェンス小説とは、公開情報や秘密情報を精査、分析して、近未来に起きるであろう出来事を描く小説である」
この物語の隠れた主人公、官房副長官の女性が次のように語りかける場面がある。 「日米の安全保障同盟とは、つまるところ朝鮮半島の有事と台湾海峡の有事、この二つの危機を想定して、それに備えるためのものなのです。でも、この二つの危機には天と地ほどの違いがあることを、あなたはよくおわかりのはずです」
これを受けて、イギリス秘密情報部の叛逆児、スティーブン・ブラッドレーは「ウルトラ・ダラーの出現から巡航ミサイル売買にいたる一連の出来事に、この台湾ファクターが影を落としている、そう見ているのですか」と畳みかけている。
「イラク戦争でのアメリカの敗北、あえてそういいましょう、これによって、東アジアでのアメリカのプレゼンスは一層軽くなってしまいました。東アジアでのアメリカの余りに永き不在は、台湾海峡をめぐる米中の軍事バランスを狂わせようとしています。経済力を背景に、中国は海・空軍力を着々と増強し、一方のアメリカは軍事的な優位を喪いつつあるのです。そのことを誰よりも良く知り、恐れているのは、ほかならぬ台湾なのです」
十四年の歳月が経ったいまなら、この官房副長官の見立てに異を唱える者はいないだろう。だが当時は、ワシントンの戦略専門家の間ですら少数意見だった。このあと、女性官房副長官は、スティーブンに李登輝に会ったことがあるかと尋ねている。
「空恐ろしくなるほど読みの深い政治家だわ。台湾海峡をめぐるアメリカの軍事力は、相対的に低下し続けている。このギャップを埋めるには日本の軍事力をもってするほかない──これが台湾の李登輝グループの基本戦略と見ていいでしょう」
私は、台湾に生まれて初の総統となった李登輝氏を台北郊外の大渓鎮に訪ねて、長時間にわたって話を聞いたことがある。万巻の書に囲まれた書斎で一九九六年の台湾海峡危機を振り返ってくれた。人民解放軍が放った四発のミサイルに台湾の人々が動揺しないよう、事前にどんな布石を打っていたのか。練達の戦略家は、采配の手の内を詳しく明かしてくれたのだった。
李登輝氏は東アジアの行く末を気にかけながら、先ごろ逝ってしまった。あの日、『ウルトラ・ダラー』を書棚に戻しながらぽつりと漏らした言葉は忘れられない。 「九六年の両岸の軍事的緊張はひとまず去ったが、海峡にはうねりが再び高まってくるはずです。今度はあなた方ニッポンが有事の当事者だよ」
これが日本に向けた李登輝の遺言だった。