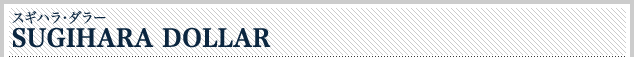「イスラエル並びにユダヤ人に関するノート(連載第17回):
手嶋龍一『スギハラ・ダラー』をどう読むか 下」
『みるとす』2010年5-6月号
前号に引き続き、外交ジャーナリスト・手嶋龍一氏(元NHKワシントン支局長)のインテリジェンス小説『スギハラ・ダラー』(新潮社、2010年)の読み解きを続ける。
手嶋氏は、第二次世界大戦中のポーランド亡命政府とユダヤ人ネットワークの関係に注目する。
<ポーランド軍はナチス・ドイツ軍に容易に降伏しようとせず、まず同盟国フランスの首都パリに、ついでイギリスの首都ロンドンに亡命政府を樹立して抵抗をやめなかった。ポーランド軍は、地下に秘密情報部を設けて、反独ネットワークを全ヨーロッパに張り巡らした。このポーランド秘密情報部に馳せ参じた士官の多くが、ポーランド国籍をもつユダヤ人だった。亡命ポーランド政府のインテリジェンス組織は、全欧ユダヤ人の情報ネットワークとぴたりと重なっていたのである。>(手嶋龍一『スギハラ・ダラー』新潮社、2010年、38~39頁)
筆者は、1986~87年、英国陸軍語学学校に留学し、ロシア語を勉強した。筆者はチェコの神学と思想に関心をもっていたので、亡命チェコ人でBBC(英国放送協会)のチェコ語海外放送のアナウンサーをつとめたスデネク・マストニク氏が経営する「インタープレス」という古本屋を週1回訪れた。マストニク氏の夫人ヘレナさんはケンブリッジ大学のチェコ語講師だった。マストニク氏は、「歩く百科事典」のようにチェコ事情に通暁していたので、筆者は同氏からチェコ思想史や共産圏事情についての講義を受けた。マストニク氏の古本屋からは、チェコスロバキアを含む共産圏で発禁になった書籍、また発禁にはなっていないが発行部数が100部以内で入手がきわめて困難な神学書を入手することができた。「インタープレス」は「アカデミックブック・エクスチェンジ(学術図書交換)」という別の名前をもっていた。そして社会主義国の図書輸出入公団とマストニク氏は興味深い取り引きをしていた。当局の忌避に触れた発禁本は社会主義国政府にとってゴミよりも質が悪い。こういう「悪書」は、書店や図書館から回収し、断裁するという建前になっていた。ただし一部の「悪書」を社会主義国政府は、西側諸国に流していた。「悪書」と交換で、西側で発行された辞書や科学技術書を入手するためだ。そうすれば貴重な外貨を節約することができる。その窓口にマストニク氏がなっていた。この仕事の意味についてマストニク氏は筆者にこう言った。「わたしたち夫婦には子供がいない。私たちが死んだ後、チェコに関する何かを残したい。ヘレナはケンブリッジ大学や英国外務省研修所でチェコ語を教え、チェコ専門家を養成することで形を残す。私は、このままだと社会主義国で抹消されてしまうことになる書籍を救い出して、大英博物館、米国議会図書館に送る。本は私が死んだ後もずっと残るからね」
マストニク氏は、本に関して不思議な原則をもっていた。マストニク氏は、ときどき本棚から本を取り出し、「この本を勧める。マサルに読む意思があるか」と尋ねる。「私が読みたいです」と答えると、その本を無料でくれる。筆者が「カネを払いたい」と言っても受け取ってくれない。その理由をマストニク氏はこう説明した。「私は本の専門家だ。本には一冊ずつ運命がある。何十年も本を扱っていると、その本が誰のところに行くのが幸せかだいたいわかるようになる。私は、私がチェコスロバキアから救い出した本がいちばん幸せな生涯を送ってほしいと思っている。この中にはマサルのところに行くのが幸せな本がかなりある。だから私はそれをより分けているのだ」
結局、筆者はマストニク氏から数百冊の神学書、思想書、歴史書を無償で譲り受けた。それはいまもとても役に立っている。マストニク夫妻に誘われ、ロンドン北部の高級住宅街ハムステッドにあるチェコスロバキア・クラブでときどき食事をした。反共系の亡命チェコスロバキア政府代表部の建物がこのクラブになっていた。そこでマストニク氏にこんな話を聞いた。
「ナチス・ドイツの英国本土爆撃を迎撃にチェコ人、スロバキア人、ポーランド人のパイロットが狩り出された。生命を英国に差し出す代償にして、祖国を失い、行き場をのない人たちはロンドンで生き延びたんだよ。そのほとんどがユダヤ系だった」
筆者が「あなたもユダヤ系なんですか」と尋ねると、マストニク氏は「残念ながら違う。私は、戦争中チェコにいた。共産政権が成立した後、亡命した。もし私がユダヤ人だったらイスラエルに帰還したよ」と笑いながら答えた。
ロンドンにはチェコスロバキア・クラブとともにポーランド・クラブもあった。手嶋氏が『スギハラ・ダラー』で展開する<亡命ポーランド政府のインテリジェンス組織は、全欧ユダヤ人の情報ネットワークとぴたりと重なっていた>という話に誇張はない。
『スギハラ・ダラー』では、オランダのビジネスマンが杉原千畝とユダヤ人ネットワークを結びつける。
<ポーランド秘密情報部がまず眼をつけたのは、カウナスで電機メーカーフィリップスの代表を務めていたオランダのビジネスマンだった。彼はオランダの名誉総領事を兼任していた。この人物に頼んでリトアニアからシベリア経由で極東に行く通過査証を発行してもらおうとした。だが、オランダは既にナチス・ドイツの占領下にあり、敗戦国が発給する査証をソ連当局が認めてくれるかどうか定かでなかった。職業外交官でない名誉総領事が発行する査証の効力にも疑問があった。
この名誉総領事は、ユダヤ難民のリーダーのひとりに重大な情報をそっと囁いてくれた。
「あなた方が極東への旅立ちを考えているなら、ウラジオストック港から海を隔ててその向こうに浮かぶ弧状列島を渡航先にすべきです。お分かりかな。そう、ニッポンです。幸いカウナスには最近日本の外交官が赴任してきた。名前はチウネ・スギハラ。彼に接触してみてはどうでしょう。あのひとなら話を聞いてくれるかもしれない」
ナチス・ドイツに占領されたオランダゆえに、こんな情報を漏らしてくれたのだろう。この情報は難民のリーダーから直ちにポーランド秘密情報部に伝えられた。「チウネ・スギハラ」とはいかなる人物か、果たしてユダヤ難民に手を差し伸べてくれる可能性はあるのか、懸命の情報収集が始まった。やがて杉原千畝がかつてハルビンにいたという情報がもたらされ、ポーランド秘密情報部からハルビンのユダヤ人コミュニティに宛てて「スギハラ情報」が照会された。三日後に暗号に組まれた詳細な回答が打ち返されてきた。>(前掲書39~40頁)
この暗号をかけられた回答という話は、もちろん手嶋氏の創作だ。もっともその文体は、外務省の公電(公務で用いる電報)ならば「事務連絡」、公信(公務で用いられる手紙)ならば「半公信」という体裁で書かれる公文書と同じだ。公式の記録に残したくない機微に触れる内容について、外務省では「事務連絡」か「半公信」でやりとりをするからだ。日本外務省の内情に通じている手嶋氏だから、こういう表現をすることができる。
<在カウナス・ポーランド武装闘争同盟殿
貴機関からの照会にご回答申し上げます。リトアニアの首都カウナスにこのほど領事代理として赴任した杉原千畝氏は日本外務省有数のロシア通として知られる人物と申し上げていい。その尋常ならざる語学力、情報収集力、交渉能力いずれをとっても、日本外務省切ってのロシア専門家の逸材に間違いありません。しかしながら、杉原千畝氏を単に外務省員と規定することは適当ではないでしょう。真の意味で「インテリジェンス・オフィサー」と呼ぶのがふさわしいと存じます。
杉原千畝氏は外務省から派遣されて日ロ協会学校の第一期生としてハルビンにやってきました。この学校は現在ハルビン学院と呼ばれております。ここでロシア語とロシアの政治・経済・社会情勢を学び、極めて優秀な成績を修めたという記録が残っています。とりわけロシア語能力については定評があり、杉原氏がついたての向こうでロシア語を話しているのを聞いたロシア人は、生粋のロシア人だと疑わなかったと証言しております。
杉原千畝氏はこの学校に入学し、その翌年、兵役に就くため一時日本に帰ったのですが、間もなく復学して、こんどはロシア語の教師も務めております。それだけ優秀な人材であったと申せましょう。
独身であった杉原千畝氏は、ハルビンの盛り場に時折出入りしていたのが目撃されています。ここで働いていた麗しい少女がクラウディア・セミョーノヴナ・アポロノヴァでした。ロシアの中部に広大な農園を所有する貴族の家に生まれたのですが、ロシア革命によってすべてを喪い、ハルビンに身を寄せたいわゆる白系ロシア人のひとりです。 当時、クラウディアはまだ十六,七の、少女といっていい年齢だったのですが、杉原千畝氏はその可憐で、少し淋しげなクラウディアの美しさ心惹かれて、やがて恋に落ちていきました。クラウディアの家系はユダヤ系なのですが、彼女はロシア正教徒でした。結婚にあたって新郎の杉原千畝もロシア正教に入信し、セルゲイ・パヴロヴィッチという洗礼名を授かっています。妻のクラウディアは夫を「セルゲイ」と呼んでおりました。結婚後、杉原千畝氏はロシア貴族でありながら東清鉄道の警備員に身をやつしていた舅の暮らしの面倒もそれとなく見ていたようです。実に心やさしき日本人でした。
杉原千畝氏は一九二四年の暮れには、ハルビン総領事館の通訳官となり、当地を去る一九三五年まで、ロシア通の外交官としてハルビンの外交コミュニティで重きをなした人物でした。外交官として、と申し上げましたが、正確には日本陸軍のハルビン特務機関に連らなる情報士官だったと言ってもいいでしょう。その後、一九三二年から三年にわたって満州国の外交部に転出してロシア科長の要職を務めております。満州里から牡丹江に至る東清鉄道を満州国がソ連政府から買い取るための交渉で辣腕を振るいます。このときの交渉ぶり、情報能力、語学力が際立っていたため、「警戒すべき人物なり」とソ連の情報当局の眼にとまったようです。杉原が単なる通訳官にとどまらない重要任務を担っていたと見抜いたのでしょう。
しかも妻のクラウディアはユダヤ人の血を引く白系ロシア貴族です。ソ連の情報当局が「反ボルシェビキ活動の黒幕として策動している」として監視の対象にしていた一族でした。加えて杉原千畝氏が在ハルビンのソ連総領事館の暗号簿を持ち出そうと、金庫のカギを管理する内報者を使った工作に従事した経歴も彼への警戒を強めたのでしょう。
ハルビンで暗躍していた怪露人チェルニエヤクをはじめとして多くの情報提供者を操っていたインテリジェンス・マスターであったことはハルビン諜報界では公然の秘密でした。
一九三六年十二月には在ソヴィエト連邦大使館勤務を命じられたのですが、ソ連当局が入国を拒否する異例の事態となりました。モスクワの情報当局が、スギハラを反ソ諜報網を操縦するインテリジェンス・マスターと見ていたと思惟できます。ソ連政府といえども日本の一外交官を「ペルソナ・ノングラータ」として赴任を拒否するのは例がありません。モスクワ当局にとっては杉原千畝氏の存在がいかに重いものであったかを窺わせましょう。
在ハルビン・ユダヤ人協会代表>(前掲書40~42頁)
そして、この情報をポーランド秘密情報部はこう評価する。
<ポーランド秘密情報部は、このハルビン情報を受けて、チウネ・スギハラという人物を徹底して分析した。そこから素顔のスギハラ像がくっきりと浮かびあがってきた。彼らの分析文書は次のように記している。
独ソ両国は、いま、一時の偽りの盟約を結んでいるが、両雄はやがて干戈を交えるにちがいない。日本政府も、錯綜する独ソ関係を監視させるため、杉原千畝を急遽派遣したものと思惟される。傑出した情報士官たる杉原千畝を『バルトの触角』としてカウナスに遣わしたのだろう。
ポーランド秘密情報部は、杉原千畝に是非とも、しかもすみやかに接触すべきだという結論に達したのだった。>(前掲書42~43頁)
もちろんこの部分も手嶋氏の創作だ。しかし、ここに杉原千畝の真実が現れていると筆者は考える。「人道という観点から、外務本省の訓令に背いたノンキャリア外交官」という切り口から見ると誤認してしまうインテリジェンス・オフィサーとしての杉原千畝の姿を手嶋氏は見事に描き出した。インテリジェンスは国策として行われる。戦前、戦中の日本に、ナチス・ドイツのような反ユダヤ主義がなかったからこそ、杉原千畝は「命のビザ」を発給することができたのだ。この真実を手嶋氏がインテリジェンス小説という手法で明らかにしたことを筆者はうれしく思う。(2010年5月20日脱稿)
作家・起訴休職外務事務官 佐藤優