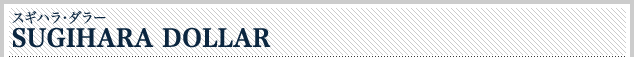戦時の試練は3人の友情を揺るぎなきものにした
手嶋龍一『スギハラ・ダラー』を読む 2010年02月19日(Fri) 河野 通和
「冷戦後、日本人によって書かれた初の本格的インテリジェンス(諜報)小説の傑作」(佐藤優氏)と激賞されたデビュー作『ウルトラ・ダラー』から4年。待望の新作、姉妹編の誕生である。
前作では、北朝鮮によるドル札偽造工作に大打撃を与えるという赫々たる戦果を挙げたにもかかわらず、そこに「重大な訓令違反」があったとして、任国日本での謹慎を言い渡されたイギリス秘密情報部員スティーブン・ブラッドレーは、北陸・金沢の蒔絵師のもとに弟子入りして無聊をかこつ日々を過ごしている。
そんなある夜、金沢市内「ひがしの茶屋」で寛ぐ2人の人物のもとへそれぞれ緊急の連絡がもたらされる。2008年9月、世界金融市場を揺るがせたリーマン・ショックの第1報であった。
連絡を受けた1人は、この日敦賀を経て、先ほど金沢に着いたばかりというシカゴ・マーカンタイル取引所のアンドレイ・フリスクと名乗る紳士。もう1人は、北浜の大阪証券取引所で「剛毅」と畏れられる相場師「松雷」こと松山雷児であった。
金融市場の異変を知らされ、ともに一世一代の勝負の時を迎えた2人であったが、お互いが指呼の間に居合わせていることも知らず、アンドレイは「買い」、松雷は「売り」の対極の構えで、大荒れの相場に挑むのであった。
だがこの2人、実は70年近く前に、神戸の地でその数奇な運命を交差させる瞬間があった。現代史の壮大なドラマは、こうして幕を開ける――。
それにしても、編集者として多少とも小説の誕生する舞台裏を見聞してきた評者からすると、この一作を書くために作者はどれほどの時間と労力、そして元手をつぎ込んだのかと驚嘆するばかりである。
それくらいに破格の作品である。全体の構え、展開のスケールも格別ならば、物語の舞台もポーランド、上海、スコットランド、スリランカ、パリ、そして米国各地、国内では金沢、神戸、湯島、浅草、北海道等々を駆け巡る。
一方、細部を彩る演出、描写は華麗な社交の場から裏社会の生態、グルメ、ファッション、旅、フライ・フィッシング、競馬とあらゆる事象にわたっている。
しかも各ピースが丹念に選り分けられ、注意深く配置されて、全体が精緻なジグソーパズルのように仕立てられているのがこの小説である。
主人公アンドレイはポーランドの古都クラコフに生まれた。だが、小学校に上がろうとした1939年9月、故国がナチス・ドイツに制圧されようとする直前にリトアニアへ逃れ、そこで在カナウス日本領事館領事代理だった杉原千畝が発給した日本の通過ビザ、いわゆる「命のビザ」を手にシベリア鉄道でウラジオストックへ渡る。そして敦賀を経由し、神戸へ辿り着いたポーランド系ユダヤ難民である。
彼はそこで、無頼の孤児・松山雷児と出会い、束の間の友情を育む。やがて真珠湾攻撃まであと数カ月と迫った1941年3月、アメリカへとさらに旅立つアンドレイと雷児には別れの時が訪れるが、その時、雷児はアンドレイから大きな「使命」を託される。
それは、やはりホロコーストの恐怖を逃れ、ポーランドから神戸に避難していたアンドレイの幼馴染みソフィーの守護神となることだった。再びヨーロッパの地へ戻りたいと願う両親とともに神戸を後にした彼女を追い、雷児は単身、魔都・上海へと旅立つ。
こうして物語は、彼らは再びめぐり合うのか、それはいつ、どのような形で、という興味に沿って展開されていく。
ところで、その後のアンドレイはやがてシカゴに定住の地を見つけるのだが、実はこの主人公には、作者が啓示を受けたと思われる実在のモデルが存在する。レオ・メラメド。アメリカ金融先物市場の父と言われ、1970年代、シカゴ・マーカンタイル取引所を舞台に先物取引を育てた大立者である。
作中、アンドレイの人となりを際立たせる逸話として、作者はひとつの「事実」を用意している。
1987年のブラック・マンデー。寄り付きから売りが殺到して銘柄のほとんどに値がつかない状況を前に、ニューヨーク証券取引所は市場を閉鎖し、全米市場の心肺機能は停止するかに思われた。
だがその時にあって、シカゴのマーカンタイル証券取引所は最後までゲートを開け続ける。いったん市場を閉じて嵐が過ぎ去るのを待つべきだ、とする声に、アンドレイは一切耳を貸さない。後になって尋ねられる。「なぜあの時、あなたは閉じなかったのか?」と。彼は答える。「それは、私がスギハラ・サバイバルだったからでしょう。そうとしかお答えしようがない」
流浪の民となり2年近くに及ぶ逃避行の果て、ようやく辿り着いた自由の国アメリカ。 「私の背後には、志半ばで斃れていった幾多の同胞がいる。彼らの遺志を継いで、自由を新大陸に押し広げていく。その先駆けとなると誓ったのです。だから、私は挫けるわけにはいかなかった。自由の国アメリカのシンボルである市場の自由な取引をなんとしても守り抜きたかったのです。自由な取引を担保するこの市場メカニズムは、私、アンドレイ・フリスクの命そのものでした」と。
かのアラン・グリーンスパン元FRB議長をして「杉原がいなければ、メラメドも、金融先物取引も、デリバティブも生まれていなかったであろう」と言わしめたスギハラ・サバイバル。
ここまででお分かりのように、この小説全体を貫く太い縦軸は「受難の民」ユダヤ人の20世紀史である。
そして、前作『ウルトラ・ダラー』の主舞台が国際政治そのものであったのに対し、今回代わって前面に登場するのは国際金融市場である。だが、そういう舞台回しの転換があったにせよ、両手嶋作品を貫く共通のモチーフは、インテリジェンス(知性によって彫琢され抜いた情報)への誘いに他ならない。
ここで作品の核心部分を明かすわけにはいかないのだが、時間・空間の差異を最大限に活かすのが資本主義の原理だとすれば、古今東西の金融市場のドラマの中で、歴史上われわれが真っ先に思い浮かべるのは、ワーテルローの戦いにおけるネイサン・ロスチャイルドの伝説ではなかろうか。
1815年6月20日朝、ロンドン取引所にいたネイサンは青ざめ、疲れ切った顔をしていた。大陸では、ナポレオン率いるフランス軍とイギリス=オランダ=プロイセン軍がワーテルローで戦火を交えているさ中であった。
もしイギリスが負けることになれば、国債を発行して軍資金を調達していたイギリス市場は大暴落する羽目に陥る。投資家たちは戦争の行方を固唾を呑んで見守っていた。その時、青ざめて表情を失っていたネイサンが、突然「売り」に走った。
公債や証券を急に売り始めたのである。ネイサンがイギリスに対して莫大な投資をしていたこと、また彼が独自の情報網を持ち、いち早くインテリジェンス(勝負の分かれ目を決する核心情報)を手にするであろうことを知っていた市場関係者は、「ウェリントン将軍は敗れた!」と受け止め、我先にと債権を売りに出す。
相場は大暴落する。ところが、この時実は、イギリス勝利の確かな情報を入手していたネイサンは、ひそかに紙くず同然の底値となったイギリス国債を買い集め、やがてイギリス軍勝利の報がもたらされて相場が急反騰した時には、ネイサンは「濡れ手で粟」の巨万の富を得ていた――。
情報は金。情報戦を制する者が繁栄の階段を上る。ユダヤ金融王国誕生の秘話としてあまりに有名な物語である。
ところが、この鉄則、勝利の方程式を使って、現代においても、このワーテルローの故事を想起させる金融市場の「大博打」が実は行なわれていた。そして、何者かによって独占的な「富の収奪」がひそかに企てられていた形跡がある。
それは誰が、どのような手口で行なったのか。必勝の切り札として、どうやって超一級の極秘情報を手に入れたのか。また、それをいかに使いこなして巨額の稼ぎに結びつけたのか。その目的は? 究極の狙いは?
この途方もない謎解きに果敢に挑むのが、生まれながらの情報士官であるブラッドレーと、その親友にして敏腕の金融Gメン、商品先物取引捜査官のマイケル・コリンズのコンビである。
まさにインテリジェンスの申し子たちが、膨大に存在する玉石混交の情報を選り分け、精査し、裏を取り、鋭い嗅覚で本線に迫り、事件を読み解き分析していくプロセスは、全編「インテリジェンス啓蒙小説」といってよい趣がある。
加えて、インテリジェンスの世界に生きる人間の心理、共通のマナー、ルールといったものが彼らの個性のうちに巧みに描きこまれていて、これもエンターテインメントの重要な要素となっている。
追う者と追われる者。最終章まで決着が見えないままに、舞台はふたたび金沢へと戻る。そして20世紀をめぐる大きな物語は近未来への預言を暗示しながら、卯辰山の端に半月がかかる北陸の夜の情景とともに締めくくられる。
なお、レオ・メラメドその人については、『金融先物の父"レオ・メラメド"から学ぶ 金融先物の世界』(可児滋、時事通信社)という好著が昨年秋に刊行された。作者がどのように「本当のような嘘」と「嘘のような本当」をブレンドさせたか、それを読み比べてみる。