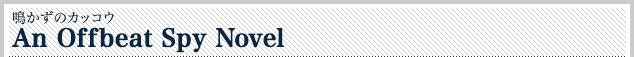「巨大情報戦の最前線描く」
海外で取材をしていると、「秘密警察」「スパイか」といった言葉を頻繁に聞くことになる。 たとえば、イランのレストランで政治の話題を振れば、「政府の秘密警察がいるからその話題はなしだ」と怒られ、ヨルダンで難民キャンプへ行こうとすれば警察に止められて「おまえはスパイか」と疑われる。
世界全体で見れば、こういう国の方が多数だろう。国は一つの情報を奪われただけで崩壊にいたることもある。だから政府は情報を守ることに膨大な予算と人材を注ぎ込み、外国の諜報機関に対する捜査網を国内に張り巡らす。時として疑惑の目は国民にも向けられるため、国民同士も疑心暗鬼にならざるをえない。良い悪いではなく、国民を守るための最低限の戦略なのだ。
こうした国から日本に帰国すると、あまりに無防備な状況にそら恐ろしくなるほどだ。 海外の諜報機関にとって日本は天国のようなところだろう。日産のカルロス・ゴーンの脱走劇を思い出すまでもなく、その気になればやりたい放題にちがいない。
本書の舞台は、そんな頼りない日本における情報戦の最前線に立つ公安調査庁の神戸事務所だ。
だが、公安調査庁は「最小にして最弱の情報組織」と言われるように、警察や防衛省の情報機関と比べても、人材面、予算面で圧倒的に乏しい。神戸事務所は所長を含めてわずか28人。三つに分かれている部門のうち国際テロ組織を監視する班はアメリカ同時多発テロをきっかけに発足した新参だ。
著者の手嶋は、こうした現実を包み隠さず明かした上で、公務員の安定性を求めて入庁した梶壮太を主人公にすえる。海外情勢に詳しいわけでなく、出世欲も名誉欲も持たない現代風の若者。そんな人材に国家の安全を託さなければならない日本の現状を見事に表している。
壮太は、入庁後にベテラン調査官たちにもまれながら経験をつんでいくうちに、世界情勢を大きく揺るがす重大情報にたどり着く。それは日本を舞台にして、世界各国の機密機関がくり広げていた巨大な情報戦だった――。
壮太の成長と衝撃の結末についてはぜひ、本書を読んでいただきたい。私が読み進めていく中でもっとも興味深かったのが、ビジネス、ブームは点と点でつながり、世界の権力構図を形成していることだ。
バングラデシュにある世界中の船が棄てられる悪名高き「船の墓場」、臓器移植などで利用される「医療ツーリズム」、スーパーの棚に陳列される中国産と銘打たれた「北朝鮮産のマツタケ」、ワイン好きの間でブームになっているジョージアの「オレンジ・ワイン」。
日本のメディアではバラバラに報じられているニュースや、愛好家の間で起こる小さなブームが、世界を舞台にした情報戦の中ではすべて点と点でつながっており、国家と国家の綱引きに利用されているのだ。壮太が行う公安調査庁の役割とは、それの関係性をひもといて背後にある国家の存在を暴き出し、日本の国益を守ることなのだ。
本書はミステリーとして秀逸であるだけでなく、気がつかないうちに私たちの日常が世界規模の情報戦に巻き込まれていることを教えてくれる。今朝の朝刊で報じられていた海外の問題、チラシで取り上げられていた商品、今夜食べようと考えていた料理、そうしたものが核ミサイルにも引けを取らない情報戦争の武器となり、国家の存亡を左右しているのだ。
日本人はもっとそうしたことを知り、敏感になり、警戒心を持った方がいい。
評:石井光太(作家)