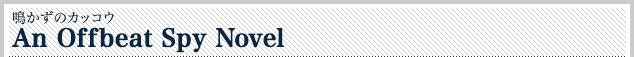茶室で高度な情報戦
金澤のひがし茶屋街から忽然と消えた英国秘密情報部のスティーブンが十年余の歳月を経て帰ってきた。前作の『スギハラ・サバイバル』で9・11テロを巡る情報戦を戦った彼は、日本海沿いの松江に姿を現した。本書の終盤では重要な役割を果たすのだが、ここでは種明かしは控えたい。
この物語の主人公、梶壮太は、脱力系にしてマンガオタクの青年。「最小にして最弱」の情報機関、公安調査庁の神戸事務所に職を得て六年。さしたる覚悟もなく調査官になり、周囲からは「使いもんにならん奴」と見られている。実は、図抜けた映像記憶装置の持ち主なのだが、本人にも自覚がない。
そんな壮太は、怪しい取引に関わる神戸の海運会社の内情を探っているうち、北朝鮮、中国、ウクライナの影が錯綜する国際諜報戦に誘い込まれていく。公安調査官の任務は、身分を偽装してヒューミント、相手から生の情報を引き出すことにある。壮太も疑惑のシップ・ブローカーの社長夫人に、茶道の弟子に成りすまして近づき、その果てに驚くべき情報のダイヤモンド鉱脈を掘り当ててしまう。
この物語には派手なドンパチもカーチェイスも登場しない。人脈を丹念に辿って地道に資料を漁り、標的を尾行して、疑惑の核心に肉薄していく。リアルで緊迫したシーンを読んでいるうち、まるで自分が情報士官になったかのような錯覚を覚えた。
本作に深い味わいをもたらしているのが茶の湯だ。戦国の武将たちは、茶室という外界から隔絶された空間で対峙し、命をかけて情報戦を繰り広げた。著者はそれを現代に蘇らせ、隠喩に満ちたインテリジェンスの世界を描きだしている。
床の掛軸や茶道具の取り合わせに秘めたるメッセージを託す亭主。対する客はその含意を読み解こうと知的な格闘を繰り広げる。壮太とスティーブンが茶室で交わす会話は情報のプロの切っ先が触れ合ってスリリングだ。
また、一椀の濃茶を回し飲むことで生まれる黙約は、今後の展開を暗示して期待に胸が膨らむ。インテリジェンスと茶の湯の親和性をここまで見事に描いた作品は類を見ないと思う。
▽評者=明石寛治・明石合同取締役副会長