
「エリート高官が陥る病癖」
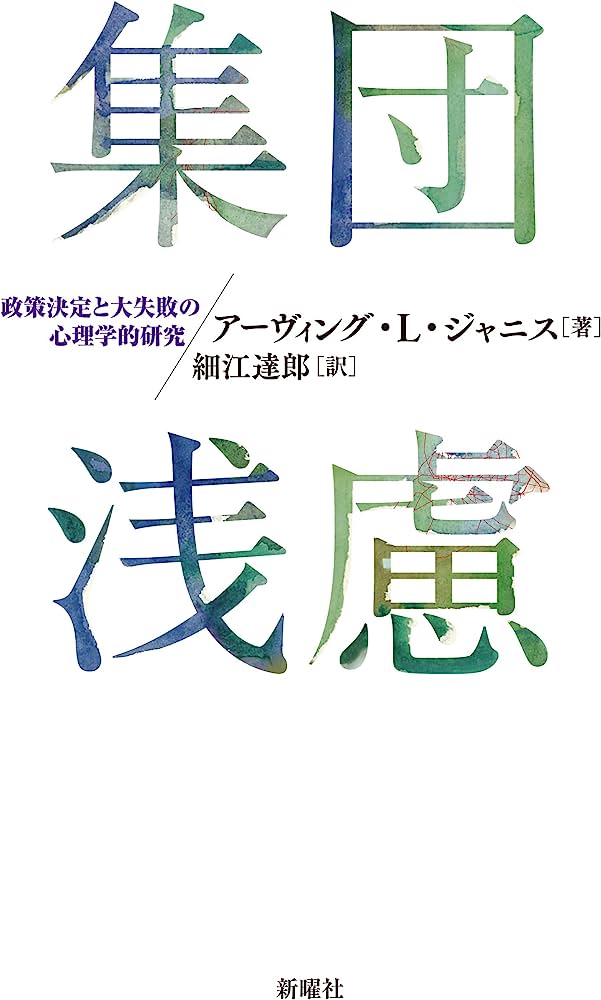 ホワイトハウスに集う“最良にして聡明”なパワーエリートが何故、大統領をかくも誤った決断に導いてしまうのか。本書は現代史を揺るがした事件に分け入ってその病弊に挑んでいる。政権の高官が全員一致の結論に拘わり、他に取り得えたはずの選択肢を見落とす様を抉りだす。groupthinkと表現される集団思考の症候群を「集団浅慮」と訳し、超大国を迷路に誘い込む元凶のひとつだと指摘する。
ホワイトハウスに集う“最良にして聡明”なパワーエリートが何故、大統領をかくも誤った決断に導いてしまうのか。本書は現代史を揺るがした事件に分け入ってその病弊に挑んでいる。政権の高官が全員一致の結論に拘わり、他に取り得えたはずの選択肢を見落とす様を抉りだす。groupthinkと表現される集団思考の症候群を「集団浅慮」と訳し、超大国を迷路に誘い込む元凶のひとつだと指摘する。
冒頭で亡命キューバ人による侵攻作戦、ピッグス湾事件を俎上にあげ、ケネディ政権の閣僚、補佐官がCIAの作戦案を鵜呑みにし、輿望を担って船出したケネディ大統領に痛打を浴びせてしまったと指弾する。コンピュータのような切れ味のマクナマラ国防長官、ハーバード大学の花形教授から迎えられたバンディ補佐官、手堅い組織運営を買われたラスク国務長官。綺羅星のような逸材を擁しながら、カストロ政権を転覆する企みの杜撰さを誰も見抜けなかった。まさしく「集団浅慮」の罠に落ちたと著者は断じている。
その失敗から二年、クレムリンはキューバに核ミサイルを極秘裡に持ち込んだ。かくして「危機の13日間」の幕はあがり、米ソは全面核戦争の淵に立たされた。未曽有の危機に立ち向かったのは、ピッグス湾事件の時と同じ面々だった。ホワイトハウスにはEXCOM・緊急執行委員会が設けられ、米国が取りうる選択肢が検討された。長く苦しい検討の末に、空軍の強硬派が主張する空爆は退けられ、穏当な海上封鎖案がケネディに示された。ホワイトハウスの賢者たちは、米国の不敗神話に惑わされることなく、全面核戦争を引き起こしたかもしれない「集団浅慮」をからくも免れたのだった。人類を破滅させる核の脅威こそ「集団浅慮を阻止するよう働いた主要な要因」だったと著者は結論づけている。
ジョンソン政権の「ベトナム戦争のエスカレーション」も失敗の例証として扱われている。政権の高官たちは幾度も錯誤を重ねて北爆に突き進み、その果てに米国の若者、5万人を死なせてしまった。これに参画したのは、ピッグス湾事件とキューバ危機に関わった同じ高官たちだった。この事実は「集団浅慮」という病弊が間欠泉のように超大国の中枢で噴き出すことを教えている。米国の強大な力を過信し、弱腰とみられることを恐れ、権力の中枢から逐われたくないと怯える。祖国を危局に追い込む芽に気づいていても口をつぐんでしまう。そんな「集団浅慮」に“賢者たち”は足を絡めとられていったのである。失敗の事例は葬列のように続き、成功の事例はわずかにキューバ危機とマーシャルプランが挙げられているにすぎない。読者は政権中枢の“賢者”に自らを重ね合わせ、慄然とすることだろう。組織にあって孤立を恐れず、堂々と自らの意見を貫き、「集団浅慮」の外に身を置くことのいかに難しいことか。それは決してホワイトハウスに限らない。
我々が日々悲惨な現実を目にしているプーチンの戦争。侵攻前、クレムリンの高官たちは独裁者を制止しようとしなかった。一方のバイデン政権も、ロシア軍が国境を侵すのは確実と見ながら、プーチンのウクライナ侵攻を抑止できなかった。双方とも「集団浅慮」の罠に落ち、戦争は長期化の様相を見せる。その果てにいま、キューバのミサイル危機以来、人類は核戦争の瀬戸際に追い込まれている。アメリカで本書の初版が出版されたのはもう半世紀も前のことだ。だが、『集団浅慮』の書には、我々がいまこそ噛みしめるべき教訓に満ちている。



