
ライス回顧録 ホワイトハウス・激動の2920日
「ライス回顧録」解説
手嶋龍一(外交ジャーナリスト)
書棚の『ホワイトハウス・イヤーズ』
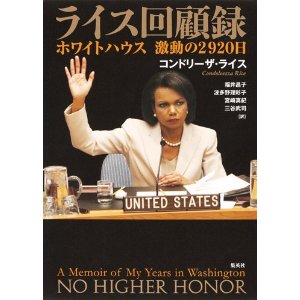 学術書がびっしりと並ぶ書棚に背表紙が傷んだ一冊の本が置かれていた。米中の劇的な接近を演出したヘンリー・キッシンジャー博士が著した『ホワイトハウス・イヤーズ』だった。そこは西海岸の名門スタンフォード大学、コンドリーザ・ライス教授の居室。気鋭の国際政治学者は、次期大統領ジョージ・W・ブッシュの求めに応じてホワイトハウスの赴こうとしていた。
学術書がびっしりと並ぶ書棚に背表紙が傷んだ一冊の本が置かれていた。米中の劇的な接近を演出したヘンリー・キッシンジャー博士が著した『ホワイトハウス・イヤーズ』だった。そこは西海岸の名門スタンフォード大学、コンドリーザ・ライス教授の居室。気鋭の国際政治学者は、次期大統領ジョージ・W・ブッシュの求めに応じてホワイトハウスの赴こうとしていた。
いつの日か我が手で現代史を紡ぎだしてみせる――。コンドリーザ・ライスは、ニクソン政権の外交・安全保障政策を思うさま操った現代外交の巨星が綴ったメモワールを手に取り、同じポストに就く自らを重ね合わせていたのだろう。共和党政権で国家安全保障担当補佐官を務めただけではない。その後、同じく国務長官に転じてアメリカ外交を率いることになった。超大国アメリカの外交・安全保障政策の舵をとる「力の司祭」として政権の中枢に入る。身震いするような緊張が彼女の全身を貫いていたことだろう。
国家の命運を賭けてくだす大統領の決断を支える。それが彼女のポストに課せられた苛烈な責務だった。それゆえ、「ベスト&ブライテスト」(デイヴィット・ハルバースタム)と呼ばれる超大国の逸材が次々にこの地位に就いてきた。ケネディ政権でキューバ危機に遭遇したマクジョージ・バンディ、ニクソン政権で極秘訪中したヘンリー・キッシンジャー、カーター政権でキャンプ・デービッド会談を実現させたズビグニュー・ブレジンスキー、パパ・ブッシュ政権にあって湾岸戦争を勝利に導いたブレント・スコウクロフト。綺羅星のようなプレーヤーがアメリカの外交・安全保障政策を差配してきたのである。
バーミンガムから来た黒人少女
「ローン・スター」と呼ばれる南部テキサス州知事から保守派の輿望を担ってホワイトハウスに入った共和党のジョージ・W・ブッシュ。このひとの最初の決断は、注目のポストに女性で黒人のコンドリーザ・ライスを充てることだった。バスで黒人が白人と同じ席に着けなかった時代に、南部アラバマ州バーミンガムに生まれたアフリカ系の女性がホワイトハウスの中枢ポストに起用される日がくるとは誰も想像できなかったろう。だが、多民族国家アメリカはめくるめくスピードで変貌を遂げつつあったのである。
黒人教会の牧師の家庭に生まれ、「コンディ」と呼ばれる並はずれて利発な少女がいた。だが、明るい少女時代を送っていた彼女も、白人の極右組織が起こした爆弾テロで大切な同級生を喪っている。やがて彼女は飛び級でデンバー大学に進み、ピアニスト志望から国際政治に転じて博士号を取得し、スタンフォード大学で国際政治学者となった。難解なロシア語をものにして、冷戦の主敵クレムリンの意図を精緻に分析できる人材になろうと外交の現場で研鑚を重ねていった。パパ・ブッシュ大統領にソ連・東欧担当の大統領特別補佐官として仕え、めきめきと頭角を現していった
「あなたの国、ソ連についての私の知見は、すべてこの女性に負っているのです」
米ソ首脳会談の席上、パパ・ブッシュ大統領はゴルバチョフ大統領にこう明かして彼女を紹介した。異例の出来事といっていい。ホワイトハウス詰めの特派員としてこの会談を取材していた筆者にもこのエピソードは聞こえてきた。対ソ外交におけるライスの存在が大きくなりつつあると感じたことを鮮やかに憶えている。彼女はこうしてパパ・ブッシュ大統領の篤い信頼を得て、テキサス州知事からわずか6年で大統領となった息子に推挙された。
名門ブッシュ家の御曹司とアラバマから来たアフリカ系の才媛。ユニークな取り合わせなのだが、ふたりは妙にウマがあった。コンディの内面世界が、白人のエスタブリッシュメントとさして変わらなかったのも一因だった。アメリカン・フットボールが好きで、モーツァルトのピアノ曲を聴き、夏の休暇はウェスト・ヴァージニア州の保養地グリーンブライヤーで過ごす。典型的なアッパー・ミドルクラスのライフ・スタイルだ。こうしてホワイトハウスで共に働くパワー・エリートたちも彼女の出自をいつしか意識しなくなった。
9・11同時多発テロの朝
あの日の朝、アメリカ東海岸の空は真っ青に澄みきっていた。
「ニューヨークのワールド・トレード・センタービルに小型機が衝突したらしい」
PBSラジオからブレーキング・ニュースが流れてきた。出勤途上の車で事件の一報に接した筆者は、果たして操縦ミスによる単なる事故なのだろうかと咄嗟に思った。8年前の一九九三年、この高層ビルの地下に爆弾が仕掛けられた。テロの実行犯は、国際テロ組織アルカイダだったことがその後の捜査で明らかになっていたからだ。
オサマ・ビンラディンに率いられたアルカイダはアメリカ本土を狙っている――。事件の直前、CIAの首脳陣は、ホワイトハウスにライスを訪ねてこう機密情報を告げていた。ブッシュ大統領に何らかの対抗措置をとるよう進言してほしい。暗にこう求めたのだが、政府部内のインテリジェンス機関を束ね、大統領に重大情報をあげる責務を担う彼女としては、簡単に応じる訳にはいかない。アメリカ本土のどこに、いつ、テロ攻撃が迫っているのか。確かなインテリジェンスでなければ、動くわけにはいかないと押し返したのだった。緊迫したやりとりがこの回顧録に記されている。
ブッシュ政権は、忍び寄る本土攻撃になんら対抗策をとらないまま時間が過ぎていった。そして、現代の真珠湾奇襲が現実になってしまう。遊説先のフロリダからブッシュ大統領は二つの軍事基地を経由して、事件当日の夕暮れ時にホワイトハウスに戻ってきた。私たちホワイトハウス詰めの記者が待ち受けるなか、ブッシュ大統領の専用ヘリコプター「マリーン・ワン」はホワイトハウスの中庭に舞い降りた。ホワイトハウス記者団の会長をながく務めるヘレン・トーマス記者が野太い声で大統領を呼びとめた。ブッシュ大統領はわずかの沈黙のあと、こう言い放った。
「アメリカを襲ったテロリストと彼らを匿う国家を分け隔てしない」
ライス補佐官はずかずかと前に踏み出し、ブッシュ大統領の腕をギュッとつかむと、オーバル・オフィスに伴っていった。大統領のこのひとことがいかに重要なものであるかを瞬時に悟ったからだろう。それはアメリカが「対テロ百年戦争」を宣言しているに等しかった。テロリストを殲滅するだけではなない。その背後にあって全世界に拡がるテロ組織を匿う国家や組織を相手に、果てなき戦いを続ける決意を闡明したからだ。その夜遅くブッシュ大統領は、執務室から全世界に向けて特別声明を放送した。ライス補佐官の諌めを振り切って、無期限、無制限の対テロ戦争を呼号する「ブッシュ・ドクトリン」がそのまま盛り込まれていた。だが本書では、大統領との緊張を孕んだやりとりについては意図して筆が押さえられているようにみえる。
知らされなかった「大統領命令」
かくしてブッシュ政権は、国際テロリズムとの果てしなき戦いに突入していった。それはいかなる国家も経験したことがない、見えざる敵との新たな戦争だった。それゆえ超大国アメリカは、従来の国際法や国内法が想定していなかった事態と向き合わなければならなかった。その最たるものがテロリストやテロリスト予備軍の拘留問題だった。
「二〇〇一年一一月一三日の夕方、私の手元に届けられてすらいない軍事命令書に、大統領がすでに署名してしまったことを知った」
ライスは怒りを行間に滲ませてこう記している。事態の推移によっては国家安全保障担当補佐官を辞任せざるをえない――。こう彼女に覚悟させた重大な事態が持ち上がっていた。同時多発テロ事件から二ヶ月後のことだった。外交・安全保障の分野で大統領を誤りなきよう導く彼女の権限が、何者かによって蹂躙されてしまったのである。
アメリカを標的とするテロリストを拘禁して裁くため、軍事委員会の設置を国防総省に命じる「大統領令」。これほど重要な命令を国家安全保障に関わる政権の枢要なメンバーに諮らないまま、大統領の署名を掠め取った者がいた。チェイニー副大統領とそれに連なる「ネオコン」一派の仕業だったとライスは断じている。
「政府でもっとも長期にわたり執拗にサダム打倒の必要性を訴えていた人々の間では、短期間だが、ある種のうぬぼれが蔓延していた。その象徴ともいうべき人物が副大統領だった」
ブッシュ政権は、九・一一同時多発テロ事件を受けて、対テロ戦争を開始するにあたって、特異な論理で武装した。ブッシュ政権の「国家安全保障戦略」に次のように書かれている。
「テロリストがわが国民と国土に危害を加えるのを防ぐべく、必要とあらば、先制攻撃によって自衛権を行使し、独自に行動することをためらうものではない」
ライスはこの「先制攻撃理論」のテーゼこそ「ネオコン」の思想を象徴的に示すものだと回想録で指弾している。だが、ネオコンが主導するブッシュ政権の一期目にあって、彼女がどこまで真剣に抗ったのか、具体的な記述は見当たらない。
イラク開戦に大義はあるか
イラクのサダム・フセイン政権は、大量破壊兵器を隠し持っていると断じて、ブッシュ政権はイラク戦争に突き進んでいった。二〇〇三年三月のことだった。だが、ブッシュ政権が開戦の大義とした情報は惨めなほどに間違っていた。
ライスは誤った情報に基づいて始めてしまった戦争について次のように述べている。
「イラク戦争は国家戦略的な知見からではなく、情報機関の見地によって正当化されてしまった」
アメリカは、国家戦略という大局的な見地ではなく、情報機関がもたらした不確かな情報に頼ってイラク戦争を安易に始める誤りを犯したと率直に認めている。
フランスやドイツさらにはカナダなど永年のアメリカの同盟国が戦争の大義に疑問を投げかけ、「ブッシュの戦争」に抗うなか、日本だけがアメリカ側から示された情報に唯々諾々と受け入れた。そして過去の国連決議をか細い拠り所にして「ブッシュの戦争」を正当化してしまった。
「『決定的証拠をつかんでいながら、きのこ雲見るようなことになってほしくないのです』。言葉は本心から出たものだ。情報機関の分析が確かなものであることはめったにない。だが、九一一を経験した今となっては、脅威が現実のものとなるまで何もしないという選択肢はなかった」
ライスは本書でこんな苦しい言い訳を書きとめている。
「どこで私は間違ってしまったのだろうか?たしかに、大量破壊兵器の問題を、より大局的な対サダム戦略と切り離して考えるようになってしまった。私は情報機関からの断片的な情報を引用すること、とりわけ大統領がそれを引用することを、認めるべきではなかった」
ライスは、インテリジェンスの魔性に魅入られていった自分を苦い思いを噛みしめながら回想している。完璧なインテリジェンスなど存在しない。それゆえ、情報機関がもたらす情報を冷徹に見分ける慎慮こそ安全保障に携わる者にどれほど求められるか、日本版NSC・国家安全保障会議を創ろうとしている人々に知ってほしいと思う。
北朝鮮政策めぐる日米の亀裂
チェイニー副大統領が率いる「ネオコン」一派とパウエル・ライスの穏健派が抜きがたい対立。この回想録は、こんな構図でブッシュ政権内部の抗争を描いている。確かに「ネオコン」一派は、彼らにとってかけがえのない同盟国イスラエルの安全保障を最優先して、イラクのサダム・フセイン政権を打倒することで、穏健派を圧倒していった。だが、圧政下にある国々に力で民主主義を押し広めたいと考える「ネオコン」一派は、東アジアの独裁国家北朝鮮に対しても、パウエル・ライスらの穏健派より遥かに厳しい姿勢を堅持していた。公正にいえば、「ネオコン」の情勢判断は群を抜いて精緻だった。金正日政権がマカオの銀行に貯め込んでいた黒い資金を差し押さえ、テロ支援国家の指定を外すことに反対したのは「ネオコン」であった。
だが、こと北朝鮮政策に限っては、ブッシュ大統領はライスら穏健派の路線に寄り添った。アフガン戦争からイラク戦争に、持てる力のすべてを中東地域に注ぎ込まなければならなかったからだ。その結果、東アジアに巨大な「戦略上の真空地帯」を創り出してしまった。北朝鮮はその空白を巧みに衝いて中距離ミサイルの発射事件と核実験に次々に手を染めていった。
この北朝鮮の攻勢のまえにいとも易々と手をひねられてしまったのは、ライス国務長官の右腕、東アジア担当のクリストファー・ヒル国務次官補だった。マカオの黒い資金を返還させられ、北朝鮮をテロ支援国家の指定から解除してしまう。だが、北朝鮮は言を左右に核・ミサイル問題を話し合う六ヵ国協議に復帰しようとしなかった。こうしたライス・ヒルチームの宥和的な姿勢は、同盟国日本との間で亀裂を深めてしまう。日本側の交渉者のひとりは、ヒル次官補を「キム・ジョン・ヒル」と呼んで、北朝鮮寄りの姿勢を批判している。日米同盟には深刻な亀裂が拡がっていった。
ライス国長官も小泉政権の後に誕生した安倍、福田、麻生の自由民主党政権を辛辣な表現で批判している。日本の読者には不快かもしれないが、そのまま引用する。
「小泉首相の退任後、日本は再び合意政治に逆戻りした。とても国を前進させることができるとは思えないような、誰とでも取り換え可能な首相が何人も続いた。私自身、訪日するのがどんどん憂鬱になってきた」
ライス国務長官は日本の保守政権をこき下ろしただけでなく、拉致問題の解決を優先する日本側の姿勢に強い違和感を表明している。
「日本人との個人的な相性も不安だった。私は日本人に、北朝鮮の核問題の解決にばかり熱心で、拉致問題については積極的でない、と思われていた。もちろん、拉致問題が悲劇であることは言うまでもない。だが、もしかして日本はアメリカの支援を得られなくなると困るというだけの理由で、六ヶ国協議の失敗を望んでいるのではないか、そんな風に感じることが多くなっていた」
こうして太平洋を挟む日本とアメリカの相互不信は増殖していった。
回想録に映しだされたアメリカの悲哀
キッシンジャー回顧録を頭に思い描いて本書を読み進めた読者は、ふたつの回顧録を隔てる溝の深さに戸惑ったかもしれない。米ソ冷戦の時代を生きたキッシンジャーの回顧録には、かつて朝鮮半島で戦火を交えた米中両国が劇的な接近を図ることで、ソ連を核軍縮交渉の舞台に引きずり出す外交の大技が息もつかせぬ筆致で描かれている。これに較べてライスの回想録がいかにも小粒に映ることは否めまい。だが、これをライスというプレーヤーの器量のせいにするのは公正を欠く。ライス自身が述べているように、彼女は調整型なのである。キッシンジャーのように、国務省や国防総省から権限を簒奪して、政権のなかにもう一つの政権をつくる強引なスタイルを採らなかった。大統領が誤りなき決断をくだす影の補佐役に徹する――。国家安全保障担当大統領補佐官の役割をこう自らに言い聞かせていた。国務省という巨大な官僚機構を率いる国務長官になってもこのスタイルは変わらなかった。超大国アメリカは六〇年代から七〇年代にかけて独力で国際社会を突き動かす力を持っていた。だが二十一世紀の今日、アメリカは「ふつうの超大国」になってしまった。国際社会でもまた調整型にならざるを得なかったのである。
しかし、ブッシュ政権内には、アメリカの強大な力と理念を信じて、一極主義を振りかざす人々がいた。新しい保守派「ネオコン」である。京都議定書から離脱し、欧州が開戦に立ちはだかるなかイラク戦争に突き進んでいった。だが、超大国といえども自らの力の限界を超えた外交・安全保障政策はやがて挫折せざるをえない。国際政治学者として、そんな現実を見通せていながら、ブッシュ大統領が「ネオコン」に引きずられていくのを止められなかった無念の思いが行間から窺える。この回想録には、比類なき力に陰りが兆している超大国の悲哀がくっきりと映し出されている。
安倍晋三内閣は、日本版のNSC・国家安全保障会議の創設に向けて、新しい法案を閣議決定して国会に提出した。「海洋強国」を目指す新興の大国中国が、尖閣諸島の領有を主張して攻勢を強めるなか、有事に際して内閣総理大臣の決断を支える官邸の機能がいかにも脆弱なことに危機感を覚えているからだろう。「日本版」というからには、アメリカの国家安全保障会議とそれを統括する大統領補佐官に倣っていることは明らかだ。国家が危機のなかにあるとき、国民から力の行使を委ねられた政治指導者はいかにあるべきか。国家安全保障担当補佐官はリーダーをどのように支えるべきか。コンドリーザ・ライスが書き残した貴重な証言は、いまの日本にこそかけがえのない示唆を与えている。



