
「決断のとき上・下」
ジョージ・W・ブッシュ著 伏見威蕃訳 (日本経済新聞出版社)
孤独な中で戦う大統領の姿
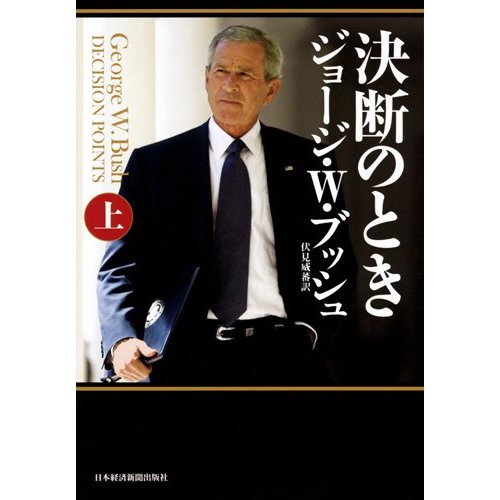 アメリカ大統領の見立てほど難しいものはない。複雑に入り組んだ50州の利害をさばかねばならず、外交・安全保障の舵取りで判断を誤れば、たちまち核の惨事を招いてしまう。ひとりの人間に次々に重大な決断を迫る大統領制のゆえに、在職中には評価が定まりようがない。
アメリカ大統領の見立てほど難しいものはない。複雑に入り組んだ50州の利害をさばかねばならず、外交・安全保障の舵取りで判断を誤れば、たちまち核の惨事を招いてしまう。ひとりの人間に次々に重大な決断を迫る大統領制のゆえに、在職中には評価が定まりようがない。
80年代の後半、ワシントンに赴任して初めて取材した大統領がロナルド・レーガンだった。「西部劇の俳優あがりが」―東部エスタブリッシュメントの知識人たちは、西海岸から来た男をあからさまに見下していた。冷戦の主敵を「悪の枢軸」と決めつけた大統領が、北米大陸にミサイル防衛の傘をかざす構想を打ち上げると「スターウォーズ」と呼んで嘲笑った。だがレーガンは全体主義の独裁体制を心から憎み、米ソの核戦争の人質に自国民を差し出す「核の抑止論」を断じて受けつけようとしなかった。揺るぎない保守派の信念こそが中距離核の全廃に道を拓き、冷戦を終わらせる原動力となったのである。かくしてレーガンはいま、リンカーンと並ぶ歴史の高みにある。
イラク戦争に突き進んで欧州の主要同盟国から単独行動主義だと批判を浴びた第43代大統領ジョージ・W・ブッシュにも再評価の日は訪れるのだろうか。すくなくとも本人はそう信じて疑わない。後の世に自分の治世を公正に評価させるにはリベラルな歴史家たちに現代史を編ませてなるものか、と自ら筆を執ったのが、回想録『決断のとき』だ。
政治家は歴史に向かって精一杯、演技するという。イラクのサダム・フセイン政権に対する戦いの記述には、自分が思い描くリーダー像がそのまま投影されている。フセインは大量破壊兵器を隠し持っていると決めつけて、武力行使に踏み切ろうとしたとき、古くからの同盟国ドイツのシュレーダー政権はブッシュ支持を躊躇った。閣僚のひとりは選挙戦でイラク戦争は国内問題から国民の眼を逸らそうとしたヒトラーと同じ振る舞いだと非難した。これに対するブッシュの烈しい怒りが行間から立ちのぼっている。
「あろうことか、ドイツの閣僚にヒトラーと較べられることなど、これに過ぎる侮辱は容易に思いつかない」
独仏をはじめとする同盟国と見解が対立した、フセイン政権による大量核兵器の保有については、信じるに足る証拠があったと述べているだけで、ブッシュ政権はなぜ誤った情報(インテリジェンス)に踊らされてしまったのか明確に触れていない。これでは歴史家のフェアな再評価も望めないだろう。
その一方で「歴史の真実はブッシュの書いている通りなのだろうな」と納得する箇所がひとつだけある。政権の命運を左右する決断は大統領自身が担ったと述べているくだりだ。9.11テロ事件を経てイラク戦争に至るまでを身近で見続けてきた者としてそう思う。アメリカ本土を初めて見舞った国際テロリズムに無期限・無制限の戦いを挑むという決定は、大統領が孤独ななかで心を決め、作戦の遂行を命じ、その結果責任をひとりで引き受けた。それゆえに本書の英文の原題も『Decision points』“決断の拠り所”としたのだろう。
選挙で選ばれた指導者が決断を下す―。そんな当たり前のことが行われていない不思議の国ニッポンにとっては、本書の主題を軽くあしらうわけにはいかないだろう。福島原発のクライシスを目の当たりにしながら、電力会社の首脳を怒鳴りつけるしか能のない指導者を戴くいまのニッポンにとって、本書は多くの示唆に富んだ素材を提供してくれている。



