
「TSUNAMI―津波」 高嶋哲夫著 (集英社)
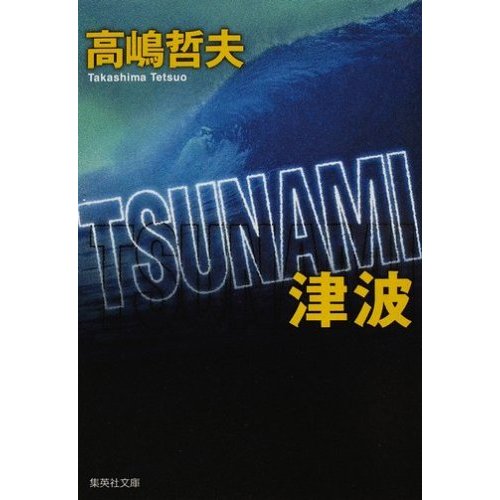 人間の想像を絶する事態を常に想定しておけ――。欧米の戦略家たちの間で語り継がれてきた心得である。米ソ両超大国が核の刃を手に対峙していた冷戦の時代、過去のいかなる事態とも異なる危機が突如持ち上がり、人類を破滅の淵に誘い込んでいった。それゆえ、現代の戦略家たちは、想像力の限りを尽くして、いや想像力の限界すら跳び超えて、人類に迫り来るクライシスと戦わなければならなかった。
人間の想像を絶する事態を常に想定しておけ――。欧米の戦略家たちの間で語り継がれてきた心得である。米ソ両超大国が核の刃を手に対峙していた冷戦の時代、過去のいかなる事態とも異なる危機が突如持ち上がり、人類を破滅の淵に誘い込んでいった。それゆえ、現代の戦略家たちは、想像力の限りを尽くして、いや想像力の限界すら跳び超えて、人類に迫り来るクライシスと戦わなければならなかった。
高嶋哲夫という作家もまた、自然災害という名のクライシスにあらん限りの想像力を注ぎ込んで立ち向かってきた。『TSUNAMI――津波』は、「災害三部作」とも呼ぶべきシリーズの第二作にあたる。彼にとって、作品のタイトルは単に『津波』ではなく、『TSUNAMI』でなければならなかった。海底で生じた揺れは、海を伝って地表を襲う。その威力は国境などたちまち無意味なものに変えてしまうからだ。
二〇〇四年十二月に起きたスマトラ島沖地震がその典型だろう。後に「インド洋大津波」と呼ばれる災厄は、二十二万人もの命を奪ってしまった。BBCワールドの特派員が「恐ろしいTSUNAMIが襲っている」と叫んだあのリポートはいまも鮮烈に憶えている。海水が恐ろしいスピードで市街地を急襲した。深さ四〇〇〇メートルの海底では、TSUNAMIの時速は八百キロにも達するという。その勢いを駆って互いに烈しくぶつかりあいながら陸地めがけてやってくる。スリランカのヒッカドゥワに停まっていた列車を高さ五メートルを超える大波があっというまに呑み込んでしまう。乗客一二七〇人が瞬時に海の魔神にさらわれて姿を消してしまった。これほどの獰猛さをいったい誰が想像できただろうか。
高嶋哲夫に「災害三部作」の筆を執らせたもの。それは、この作家が阪神淡路大震災に神戸で遭遇したからだろう。だが、あの悲劇はずっしりと重かった。眼前で起きたがゆえに、現実は大津波のようにこの作家を呑み込んでしまった。そこから懸命に這い出す道筋から「災害三部作」が誕生した。第一作目の『M8』には、阪神地区を襲った大震災をかろうじて生き残った三人の若い男女が登場する。その三人がこんどは東京を直撃した巨大な直下型地震に遭遇し、そのすさまじいばかりの破壊と立ち向かう物語だ。続く第二作の『TSUNAMI』は、『M8』から六年の歳月が経った日本が舞台となっている。平成大震災の時にはポストドクターだった瀬戸口誠治は、日本防災研究センターの研究部長に、瀬戸口の同級生、松浦真一郎は陸上自衛隊の一等陸尉に、そして河本亜紀子は防災担当副大臣として、新たなクライシスに臨むことになる。
物語では東海・東南海・南海の三つの海溝型地震が鎖のように絡み合い、大津波が発生。これによって日本列島の半分を呑み込んでしまう。常の作家ならこの悲劇を小手先の筆遣いで描いてしまうところだ。だが高嶋哲夫は豊富なデータを駆使して、科学的合理性に徹して、ストーリーを紡いでいく。まず東海地震・東南海地震の発生によって、名古屋地区が壊滅する。さらに東海地震・東南海地震・南海地震が連鎖し、伊豆半島から四国へと広がる巨大地震に膨らんでいく。そして三つの地震は互いに共振し、高さ二〇メートルを超える大津波が日本列島に押し寄せる。人々はこの圧倒的な災厄に必死で抗い、壮大な人間ドラマを繰り広げていく。
「我らが地球は、九十九パーセントの確率で温暖化への道を辿ることになろう」
アメリカ連邦議会上院の公聴会で航空宇宙局のジェームズ・ハンセンが述べた言葉だ。地球温暖化への警告はこの日から始まったと言われる。だが、私もこのときワシントン特派員として、米議会を担当していたのだが、私自身を含めてどれほどの人々が、このハンセンの警告を真剣に受け止めたことだろう。『沈黙の春』のレーチェル・カーソンの暗い予言にも耳を傾けようとしなかったように、どこか別のプラネットでの出来事としかとらえなかった。高嶋哲夫もまた「自然災害は、とりわけ巨大地震や大津波は、将来起こるか否かが問題なのではない。それが、いつ起こるか、どのように起こるかが問題なのだ」と警鐘を鳴らす。災害三部作の最後の作品『ジェミニの方舟』で作中の人物にこう言わせている。
「それは、この国に住む国民すべてに共通した運命なのだ」
こうした運命に立ち向かうため、物語ので「自然災害研究対策庁」構想を提唱している。アメリカのFEMA(連邦緊急事態管理庁)を念頭に置いているのだろう。しかし、どんな立派な組織を立ち上げても、自然の力を完璧に鎮め、支配することなどかなわない。われわれ人間になしうることは、災厄が襲いかかってきたときに災害を最小限度にとどめることでしかない。
「刃物と一緒に洗濯機に入れられたような」。高嶋哲夫は、獰猛な津波という災厄をこう表現している。政府の防災機関が様々な形で公表するデータより、この一言は人々の想像力をどれほどかきたてることか。大津波が来たら、遠くへ逃げるだけでは、生き残れない。すばやく、もっと高い所へ。災害が去った後のことなど気にかけるな。生き残ることだけに心を砕け――。著者は読者にこう呼びかけている。その意味で本書は、単なるデータの集積ではなく、大津波に想を得たエンターテーメント小説でもない。日本に突然変異種のように現れたサバイバル小説なのである。



